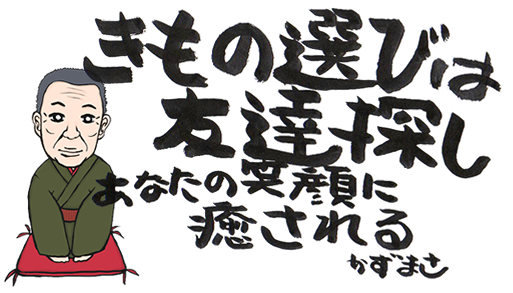
第1000号 2025年4月18日「弟」
 私には、17歳違いの弟がいた。彼には二人の子どもがいたのだが、その子らが一番かわいい盛りの頃にうつ病を発症し、家業からも家族からも離れて、一人で生活するようになった。その後、病に倒れ、4年前、53歳で他界した。好き勝手に生きてきたから、本人にとっては満足のいく人生だったかもしれないが、我々周囲の人間は振り回されてきた。
私には、17歳違いの弟がいた。彼には二人の子どもがいたのだが、その子らが一番かわいい盛りの頃にうつ病を発症し、家業からも家族からも離れて、一人で生活するようになった。その後、病に倒れ、4年前、53歳で他界した。好き勝手に生きてきたから、本人にとっては満足のいく人生だったかもしれないが、我々周囲の人間は振り回されてきた。
亡くなった時、私は70歳。とっくに定年は過ぎていた。本当なら、もっと早くに社長の代替わりをしているはずだった。親父は、私が50歳の時に亡くなった。私が仕事を始めた頃から、考え方が違うからか、相性が良くないからか、父とは折り合いが悪く、生前、『社長は弟に譲るから、お前はいつでも出ていきなさい』と言われていた。番頭から言われ、店を継いだが、継いでみてわかったことがある。父と弟、二人とも後始末の出来ない人間だった。祖父もそうだったから、私の家系はそうなのかもしれない。困ったものだ。私はそうならないよう気を付けねばと思っている。
第999号 2025年2月21日「反省 No.2」
No.1でも述べたが、商いの初めは、名簿を購入して、その名簿にあるお宅の訪問からお客様を作っていった。
大型着物専門店や同業の組合、問屋が運営する小売店の集まり等が立派なパンフレットを作るようになると、小さな小売店は、そういう類のグループに加入することにより対応した。振袖を売るための勉強会も開かれた。産地見学もした。
次に現れたのはITだ。ITならブランド、色、サイズ、タイプ、値段など、商品検索すれば瞬時にいくらでも見られるし、購入もできる。そんな時代になった。インターネットをうまく利用すれば、『うちは店の立地条件が悪いから…』などと心配することもないのだ。
個人情報である名簿は、50年前は役所で購入できた。テレアポも、30年前は話法の勉強会があった。だが、現在は悪行とされ、SNSで『書き込み』される。我が店は7年前からテレアポは私一人でやってきた。だから、話し方が悪いと言われれば、私が悪い話し方をしたのでしょう。申し訳なく思います。今後、名簿でのテレアポは一切いたしません。
今後とも正直屋をよろしくお願い申し上げます。
第998号 2024年12月27日「反省」
着物業に携わるようになってから55年になる。丁稚(でっち)奉公時代も含めた年数だ。
実家に戻り、正直屋での商いを始めた頃は、当然のことながら、私のお客様はひとりも無かった。役所で成人名簿を購入し、そのリストにある家を一軒ずつ訪問してお客様を増やしていった。店舗が増え、番頭のお客様を譲り受け、フォローしてもらいながらの商いだった。『正直屋友の会』の会員数も増やした。そんな努力の積み重ねで、招待旅行に参加いただくお客様が私ひとりで50人ほどになった。店も4店舗になり、我店だけで名古屋の中心地で展示会を開けるようにもなった。順調だった。
平成9年に親父が亡くなり、私がその跡を継ぎ代表者となった頃から、着物業界が徐々に悪くなっていった。番頭たちが定年退職する頃には、長者町の繊維問屋でも、倒産する店が多くあった。東海呉服組合が解散する頃には、廃業する店が出た。着物は購入するものではなく、レンタルするものと徐々に変わっていき、常着を購入する人も減っていった。
親父が亡くなると、私は、お客様訪問をする時間を以前のようには取れなくなった。また、目の病気を患い、平成15年くらいからは運転もできなくなった。仕事をホームページやDM制作等に変えざるを得なくなった。従業員も減り、店も2店舗に減らした。
着物屋に生まれながら着物販売ができなくなってしまった私だが、まだできることはあると思っている。営業日には、毎日着物姿で店に出る。祖父・奥田正直がそうであったように、それが最後の姿でありたい。
第997号 2024年10月22日「振袖21グループ」
 15年間やらせていただいた振袖21グループの理事長を、今年の6月末日で退いた。この間、様々な問題が起きたが、その時々の理事にご協力いただきながら解決してきた。何とか黒字のまま退任できたことはよかったと思っている。
15年間やらせていただいた振袖21グループの理事長を、今年の6月末日で退いた。この間、様々な問題が起きたが、その時々の理事にご協力いただきながら解決してきた。何とか黒字のまま退任できたことはよかったと思っている。
我々グループの主な事業は、グループオリジナルパンフ(Rebornパンフ)の制作である。掲載柄の選択は、グループ主導で行う。『かわいい系』『モダン・クール系』『古典』と、お客様のあらゆるお好みに応えた品揃えが必要だ。選品は、すべての加盟店が参加して行うのだが、問屋さんが前もって探して用意しておいてくださる。我々の満足のいく商品を探すというのは、大変なご苦労だと思う。毎年、良い商品をご提供いただいて大変感謝している。
パンフレット制作においては、一冊当たりの単価の値上がりに、毎年頭を悩ませている。制作会社の方には、限られた予算内で、振袖モデルの選別や動画制作の提案もしていただいている。資金繰りのことを考えると、今、グループの一番の課題は加盟店を増やすことだ。
このグループは、販売促進に関する新たな挑戦や各店が抱える問題点の解消など情報交換の場でもあるから、少しでも長く参加したいと考えている。加盟店の皆様、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
第996号 2024年8月21日「日本の行事 No.2」
 戦後生まれの人の子ども・・・つまり私世代の子どもの年代は40才台が多い。それらの人の子(私からみると孫)の中には、もう成人式を迎えた人もある。
戦後生まれの人の子ども・・・つまり私世代の子どもの年代は40才台が多い。それらの人の子(私からみると孫)の中には、もう成人式を迎えた人もある。
高度成長期だったということもあり、私の親世代は、競って着物を購入した。戦争体験者である彼らは、自分たちが着飾ることができなかったから、その反動があったのかもしれない。子を思う親の気持ちに応えて、喜んで着物を着てきた人たち、その反対に着なかった人、着れなかった人もある。
着ることのなかった着物は、しつけ糸が付いたままの状態でしまい込まれ、孫が着るかもしれないと残しておいても、孫も着ないとなると、ゴミになってしまうわけです。
子を思って作ったものがゴミになってしまう。しかし、それは、その親が、着物を着せる意味を教えてこなかったからではないだろうか。まずは自分が着ること、そして七五三などの通過儀礼には子どもたちにも着物を着せて、可愛い、キレイと親子で楽しんでいる家庭では、着物をゴミにするようなことはないと思う。
第995号 2024年7月19日「日本の行事」
最近、改めて日本の行事について考えるようになった。特に『宮参り』と『七五三参り』。昔は、乳幼児の死亡率が今よりずっと高かった。だからこそ、そういう通過儀礼を日本人は大事にしたのだ。
『7才までは神のうち(神の子)』という言葉がある。数え7才まで生きられない子どもは少なくなかった。諸説あるようだが、7才までは神様から子どもを預かっていて、亡くなるというのは、その預かっていた子どもを神様にお返しする、という意味のようだ。7才を迎えると、初めて社会の一員として認められた。
昔の日本人の多くは農民だった。田畑の水は村全体で管理した。田植えや刈り取りも集団で協力して行っていたから、成長した子どもというのは、村の働き手として貴重な存在であったわけだ。数え7才で行われる儀礼は、地域社会にとっても大変おめでたい行事であったことだろう。日本人のルーツの基本は、共生の魂であり、それで日本の行事が続いているのではないかと思う。
第994号 2024年6月9日「古着売買について No.7」
 私は昭和25年生まれだ。おばあちゃん子で、祖母から家業(着物屋)の話をよく聞かされた。戦中、戦後まもなくは、古着の売買もしていたらしい。鶴舞の地は、当時、名古屋のはずれ。結構お金持ちの人も多く住んでいて、そんなお金持ちの方が持ち込む品は質も良く、正直屋は良い古着を持っているという評判が広がり、よく売れたとか。
私は昭和25年生まれだ。おばあちゃん子で、祖母から家業(着物屋)の話をよく聞かされた。戦中、戦後まもなくは、古着の売買もしていたらしい。鶴舞の地は、当時、名古屋のはずれ。結構お金持ちの人も多く住んでいて、そんなお金持ちの方が持ち込む品は質も良く、正直屋は良い古着を持っているという評判が広がり、よく売れたとか。
着物を米に替えた時代があった。だから、現在80代や90代あたりの人たちは、何かあった時のためにと着物を買っては持っていた人もあったようだ。しかし、今は違う。商品はいくらでもある。
今、古着を購入される方は、よほど着物が好きな方か、芸事や仕事で着物を着る機会の多い方々だ。一般の人が着物を着用するのは式服が多く、いくらでもレンタル屋がある。わざわざ他人が着た古着を買うことなど考えない。自分の好みに合った柄やサイズの品を探すことも大変だ。古着屋のほうも、売れるかどうかわからない品など、よほど安価でなくては在庫として置けない。難しい商いだ。
第993号 2024年5月29日「古着売買について No.6」
長く着物業に従事していると、私が販売した着物を『買い取ってほしい』と言われることもある。とても悲しい気持ちになる。購入された時は、とても喜んで買われたハズなのです。『もう要らないから』と母親の着物を処分される方もある。これも、とても辛い。
せっかく買った着物を一度も着用されていない方に、それはなぜなのか聞いてみたいものだ。持つ楽しみや見る楽しみがあることは理解しているつもりだが、ぜひ着用していただきたい。ご主人や知人など、その姿を見たたくさんの人から、褒められ、羨ましがられた、という話を聞きたかった。着用されなかった着物が二束三文の値段で引き取られ、販売されていく。元の所有者の思い入れも知らず、お祓いをされることもなく、次の人は着られるのでしょう。喜んで利用されれば、眠っていた着物も日の目を見て輝くだろうか?
第992号 2024年5月20日「古着売買について No.5」
昔、古着は質屋で購入するものだった。現代はインターネットの時代。一回着用したら、もうそれでよいとばかりに、振袖をフリマアプリに出品して販売する。自分のものとして何度も着たり、悉皆に出したりなんてことはしない。
楽天やメルカリで、自分のサイズに合う、安価な振袖を探して購入。使用したら再びフリマアプリで販売する。そんな若い方もある。
着物に対しての付き合い方がずいぶん変わった。持てば保管に注意を払わねばならず、対応によっては利用できなくしてしまうこともありうる。それに対して、レンタルは気軽に利用することができることから普及していった。
昔は、着物のお手入れは、夢を膨らますひとつの楽しみだった。何かのお祝い事の折には、自分が一番好きな着物を着て出掛けて楽しんだものだ。
AIを使って出席する顔ぶれを予想して、次の会の着物をフリマアプリで探す…そんな着物好きもおもしろい。
第991号 2024年5月9日「古着売買について No.4」
古着売買の成立には、値段や品質やサイズが大きく関わってくる。
売る側は、少しでも高値で売ろうとする。買う側は、なるべく安価で品質が良く、できれば自分のサイズに合ったものを購入したいと思う。ブランド品や新品であったら尚良い。
戦前の女性の平均身長は150cm未満、現在とは10cm近くの差がある。裄(ゆき)も同じように4cmほど違う。大概は、自分好みの色柄だけを見て購入してしまうので、直し代金が高額になってしまったり、中には直しのできない品もあったりする。
高品質の品を安価で手に入れたいと思うなら、まずは和服のことを勉強し、メジャーを持って古着屋さんに行くことだ。そしてTPOも考えた上で、自分自身が納得のいく買い物をしてください。
